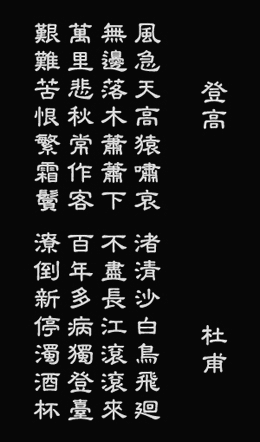 |
登 高 杜 甫 風急に天高くして 猿嘯哀し 渚清く 沙白くして 鳥飛び廻る 無辺の落木 蕭蕭として下り 不尽の長江 滾滾(こんこん)として来る 万里悲秋 常に客となり 百年多病 独り台に登る 艱難 苦(はなは)だ恨む 繁霜の鬢 潦倒(ろうとう) 新たに停む 濁酒の杯 |
【詩 形】 七言律詩 〔押韻〕 哀・廻・来・薹・杯 【語 釈】 登 高=陰暦九月九日重陽の節句に高台に登って厄払いをする風習があった。 風 急=風が強い 天 高=空が高く晴れ渡っている。 猿嘯哀=猿の長くひっぱって鳴く声が哀しくひびく。 詩では猿はしばしば哀しいものとして捉えられている。 渚 =河の中洲。岸辺というとらえかたもある。 無辺落木=果てしなく広がる落葉樹の葉 簫 簫=風の音・ここでは落ち葉の散る音の形容 不 尽=尽きることのない。「無辺」に対応している。 滾 滾=水の流れる(さか巻く)形容。 万 里=はるか遠く故郷を離れる意。 他に「悲秋」の修飾語と捉え、見わたす限りの意に取る説もある。 悲 秋=もの悲しい秋。 作 客=旅人となっている。(注※) 百 年=一生涯。生まれてこのかた。 臺 =台・ここでは高台 艱 難=さまざまな苦難。 苦 恨=ひどくうらめしい。「苦」は副詞で、はなはだしい意。 繁霜鬢=霜が降りたように白くなった揉み上げの毛。 鬢 =耳ぎわの毛。 潦 倒=老いぼれるさま。 新 =近ごろ~したばかり。 濁酒=にごった酒・どぶろく。 (注※)漢字「作」について 作の文字は日本語では「製作、つくる」等で使いますが 中国語では「 ○○ する」の意味があります。 ここでは客をする・・・、客をするはおかしいので客になるとなります。 |
【杜 甫】盛唐の詩人。(712年~770年) 後世、詩聖と称える。 鞏県(現・河南省)の人。 詳細は7言律詩「曲江」を参照 |
 |
 |
【詩の心】この詩は、杜甫56歳の作である。全ての句が対句であり、内容と表現法が見事に一致した完成度の高い詩となっている。 後に明時代の詩論家「胡応麟」が、ひとり杜甫の七言律詩として最もすぐれているばかりでなく、古今の七言律詩みなこれにかなうものはないと、批評するものである。 【登高とは】 「登高」とは、年中行事の一つとして毎年旧暦の九月九日、手近な山に登って酒宴を開くことである。新暦では十月の初旬から半ばで秋は深い、山上の高楼から晩秋の世界を俯瞰しての感懐であり、きびしい晩秋の自然のなかに、百年の憂いを抱きつつ苦悶する杜甫の言葉は悲壮をきわめ、豪快をきわめる。 詩はそのはじめからして、すでにはなはだ切迫する。「風急に天高くして 猿嘯哀し」風は山上なるが故に、非常にはげしく山上から見る天空はいよいよ高い。風はすべてをふき はらわんとするごとくに吹き、天のとばりは高く高くまきあげられたままである。 広大で空虚で、ただまっさおな空間、それが今や杜甫の前にある。あたかもその空間をかき むしるように、風がときどき運んでくるのは、猿のなき声、聞えてはまた消える。 それは、古来の詩人が争って説くように、至ってかなしい。 「渚清く 沙白くして 鳥飛び廻る」 前の句と対句になったこの句では、視線は山すその方へむけられる。 はるか下に、長江の流れが透明な空気を通してありありと見える。秋のなぎさはすみ、砂浜の色は目にしみるように白い。その上を鳥が一羽旋回するように飛んでいるのがここからやはり下の方に見おろされる。 天も地も骨格をむき出しにしたような、清浄ではあるが、きびしくそっけない風景。 天地の間には透明な空気が一ぱいにつまり情緒的なもの、雰囲気的なものは、何ひとつない。あるものといえば、こうこうと吹きわたる風。透明な空気に亀裂を作ってなく猿。おなじとこ ろをぐるぐると飛ぶ鳥。 しかし、こうした自然の中にも何か大きくざわめき、うごめくものはないであろうか。 杜甫はじっとそれに耳をかたむける。 「無辺の落木 蕭蕭として下り 不尽の長江 滾滾として来る」落木とは、落ち葉する木である。既に葉のまばらになった木は、吹きつける突風に葉をさらわれ、葉は蕭蕭と音をたてて下(ち)る。視界の限り無辺際にひろがる落葉の林、林が無辺際 であるとともに蕭蕭の音も無辺際である。かさこそと散る葉の音は、もはやささやきではない、耳をすませば大きなざわめきとなって、天地の間にみちみちる。空虚な空間にみちみちる。更にまた長江は、あたかも巨大な動脈のように、大きくうごめきつつ流れている。あとからあとからつきせぬ波が無限にもりあがりもりあがって、滾滾と、わき立つように流れている。 杜甫が天地のざわめき、うごめきをいうときは、いつもきっと彼自身の人生のうごめき、ざわめきをみちびき出さんとしてである。 この詩においても、杜甫は今やみずからの苦悶を表白してよい。いや表白せずにはおれぬ。 「万里悲秋 常に客となり 百年多病 独り台に登る」 郷国を去ること万里、おのれはいつまでもいつまでも客(たびびと)である。 人生百年、その半ばはすでにすぎたというのに、栄達・功名・みなわが身の上にはない。 わが身の上にあるものは多病である。孤独である。きょう九月九日の登高の佳節にも、たったひとりでこの高台にのぼっているのが、私だ。不平の心は、落木とともに蕭蕭として鳴り、悲哀は長江の水とおなじく、あとからあとからとわきあがらざるを得ぬ。 「艱難 苦(はなは)だ恨む 繁霜の鬢 潦倒(ろうとう) 新たに停む 濁酒の杯」 艱難とは、社会と個人の上におこる種種の困難不幸を総括した言葉であり、潦倒とは、絶望の結果おこるなげやりな生活態度をいう。 自分の一生は、艱難の連続であり、鬢の毛はおかげで、繁き霜のごとくである。老いはすで にわが身におとずれているが、しかし志はとげられない。それが自分には恨めしくてたまらな い。苦しいほど恨めしい。 論語には「四十五十にして聞(な)なき者は、言うにたらざるのみ」というではないか。 また友人李白がよく噂する阿部の仲麻呂という人物の国の詩人も「おのこやもむなしかるべきよろずよに語りつぐべき名は立てずして」といったというではないか。 自分は、潦倒たる気もちにならざるを得ぬ。世の中に相すまぬとは思うけれども、なにかなげやりな気もちにならざるを得ぬ。更に近頃は自分の生活を一そうなげやりにさせるものがある。医者から酒を禁じられたことである。「新たに濁酒の盃を停めた」ことである。 せっかくの佳節にも酒を飲むことが出来ない杜甫は、そういってこの詩をむすんでいる。 (参照:吉川幸次郎「新唐詩選」より) |